– atmaCup #20 in collaboration with Udemy 開催記念レポvol.2-
データサイエンティスト育成において「もっと技術力やスキルのある人材を育てたい」そうした課題を感じていませんか?ーそう考えていても、社員が実践的に学ぶ機会を提供し仕組化していくことは簡単ではありません。そんな中、株式会社ディー・エヌ・エー(以下 DeNA)のAI技術開発部では、社員がデータ分析コンペティション(以下、コンペ)に参加することを組織的に支援し、技術力と自走力を高める取り組みを続けています。
今回は、AI技術開発部・副部長の藤川さんと部員の村上さんへのインタビューをもとに、企業が社員のコンペ参加を支援する意義とその効果についてご紹介します。この夏、データサイエンティストの方向けに実践的な学びの場として用意しているオンサイトデータコンペティション「atmaCup #20 in collaboration with Udemy」のお知らせもありますので、ぜひ参考にしてみてください!

■藤川 和樹さん
株式会社ディー・エヌ・エー IT本部 AI・データ戦略統括部 AI技術開発部 副部長/
データサイエンティスト/ Kaggle Grandmaster
スポーツ・ゲーム・エンタメ・社会課題解決など多事業展開する同社において、AI活用技術をもとに「業務効率化・新規事業開発・既存事業の強化」といった3つの課題に取り組む事業横断組織 AI技術開発部の副部長を務める。

■村上 直輝さん
株式会社ディー・エヌ・エー IT本部 AI・データ戦略統括部 AI技術開発部 AIイノベーショングループ/データサイエンティスト/ Kaggle Grandmaster
新卒入社3年目のAI技術開発部所属メンバー。既存ゲーム事業におけるAI技術の活用や、4月に同社の100%出資で設立された子会社「DeNA AI Link」にて、toB向けAIコンサルティング・ソリューション提供サービスに関わっている。
\文字より動画で学びたいあなたへ/
Udemyで講座を探す >INDEX
コンペで育てる、社員の”広く深い技術”
ーー藤川さんのチームでは、Kaggle(*)社内ランク制度など社員のコンペ参加を支援する環境が整っているとうかがっています。なぜ、組織として社員のコンペ参加をサポートする取り組みを行っているのですか。
藤川:
当社は様々なドメインでサービス展開する事業会社です。さらに1つの事業を切り取っても、幅広い分野の技術を活用しながら、コアとなる技術については世界トップレベルの専門性を発揮することが求められます。サービスの理想とするUX実現のために、この広く深い技術が欠かせないのです。
このような状況の中で、データコンペは技術者の成長機会として非常に有効です。2-3か月という短期間で、先端技術や参加者のアイデアをキャッチアップし課題解決の引き出しを増やすという、業務でも活用できる経験を効率的に得られる場として参加を推奨しています。加えてコンペ上位入賞の実績を対外発信することで、さらに優秀な人材にリーチし採用を加速するといったブランディング効果も期待しています。
*Googleが運営する世界最大級のデータ分析・機械学習コンペティションのプラットフォーム。企業や団体が実際の課題とデータを公開し、世界中のエンジニアや研究者が最適な分析モデルを競い合う場となっている。初心者からプロまで参加でき、学習・交流・実績づくりが可能なコミュニティとしても機能。
ーーコンペへの参加を通じて、社員にこんな風になってほしいといった期待はありますか?
藤川:
自走力を身に付けてほしいといった思いはあります。Kaggleなどのデータコンペへの参加を通じて、論文や関連分野を調べてどのように最先端の技術を身に付けるか試行錯誤するノウハウが習得できると、実際の業務で必要な技術を調べるときにも自走することが出来ます。またKaggle上位入賞のためには、データを本当に深く見てちょっとした異変に気付くことができるかが重要ですが、実務においてもデータをしっかり見て仮説を立てて対策を打つといった能力発揮が期待できるのではないでしょうか。
業務時間の50%でKaggleに挑戦?!具体的なコンペ支援制度とは
ーーコンペへの参加を支援する制度について、具体的にご紹介いただけますか?
藤川:
Kaggle社内ランク制度というものがあります。前年度のKaggle実績に応じて、業務時間の20%~最大100%をKaggle参加のために利用して良いという社内ルールです。加えてコンペ参加に必要なGoogle Cloud Platformの代金を、月20万円まで会社がサポートしてくれます。制度だけがあるわけではなく実際に活用もされており、村上君も業務時間の50%を行使してKaggleに参加した経験があるうちの一人です。
ーーKaggleのようなコンペで身に付けたスキルを、実務に活かしてくれた社員がいれば教えてください。
藤川:
まさにここにいる村上君ですね(笑)
村上:
そうですね(笑)色々なコンペに参加して初めての分野や技術に触れて学んでいくということが多かったので、そこで身に付けたキャッチアップ力のようなものは実務に活きたなと思っています。技術的な点でも、どういう風にデータを処理して評価すべきなのか、あらゆる角度から考える基礎体力のようなものを身に付けることが出来ました。
評価はコンペ”実績”ではなく事業価値への還元
ーー人事評価において、コンペへの参加をどのように位置づけていますか?
藤川:
Kaggleのメダル獲得自体を成果として評価することは難しいので、メダル獲得や上位入賞という結果を会社の価値としてどう還元できるかを目標として定めてもらっていますね。例えばKaggleの上位入賞結果を外部発信して採用応募人数を増やすとか。また新しい技術分野のコンペにチャレンジして上位入賞するところまでやり切ることが出来れば、その分野で新しい案件が生まれた際にテックリードとしてアサイン出来るなど、会社としても案件創出のケイパビリティが増えたという形で評価出来ます。
ーーコンペへの参加数について、目標のようなものはありますか?
藤川:
参加数について明確な目標を持っているわけではありません。ただKaggleでの上位入賞の件数が対外的なブランディングや露出を続けるうえでのKPIになり得るため、メダルの獲得数について前年度と同等以上のペースを保てているかといった点を、一つの基準として意識しています。
自分のアイデア次第で上位に!コンペ参加の魅力
ーー続いて村上さんにもお話をうかがいたいと思います。初めてコンペに参加されたのは、いつ、どんなタイミングでしたか?
村上:
大学2、3年生くらいの時です。Kaggleというものがあるらしいと聞いて、ちょうどGCPの無料クレジットが付与されるトライアルがあることも知っていたので、ちょっとGCPを触ってみるついでにコンペもやってみようかな、と思いました。その時は全然勝てなかったので、すぐやめてしまったのですが、その後、友人経由で機械学習の学生団体を立ち上げないかという話をもらい、それならKaggleをもう一回再開してみようとなったことが、コンペに本格的に参加し始めたきっかけですね。
ーー学生と社会人では時間の使い方が変わってくるかと思うのですが、DeNAに入社された後は、どのようにしてKaggleへの参加時間や勉強をする時間を確保されていますか?
村上:
最近は結構忙しくなって試行錯誤中ではあるのですが、今までは業務時間を使ってKaggleをやっていいという社内制度を利用していました。ただそれだけでは時間が足りないので、起きている間や空いている時間はずっとKaggleをやっていましたね。一時期は、全く外出せずKaggleばかりやっているという状態になっていたと思います。
ーー村上さんがそこまで夢中になるコンペの魅力って、どんなところにありますか?
村上:
自分の順位が上がることや他の参加者に勝つことがすごく楽しいです。自分が効果的だと思ったアイデアや手法を試して、実際にモデルの性能が向上したときは本当に嬉しい!さらにそれを提出してみたら、順位が大きく上がっていたり他の参加者をごぼう抜きしていたりする。そこにすごく達成感がありドーパミンが出てきます。そういった自分の考えを予測モデルに反映して、その成果がスコアとして実感できる部分が、自分の大きなモチベーションになっていますね。
コンペで得たものは「自信」と「肌感覚」
ーーコンペに参加したことで、実際の村上さんのお仕事にどんな影響がありましたか?
村上:
自信がつきました!入社当初はKaggleの成績も飛び抜けていたわけではなく、他に実績のある方が周りにたくさんいたので不安もありましたが、コンペで優勝や金メダルなど成果を積み重ねていくうちに技術的な自信が持てるようになりました。どれくらいの労力でどれくらいの性能が出るかという「肌感覚」が養われたことは良いポイントだったと思います。
ーーデータサイエンティストとして、ビジネスパーソンとして、今後の目標があれば教えてください。
村上:
まず一つ目は、自分が扱ったことのない技術領域のコンペに参加して、知識や経験を積んでいきたいと考えています。また最近は、人材育成にも興味を持つようになりました。人工知能オリンピックの日本委員会で理事を務めているのですが、そのような活動を通じて後進育成やAI・データサイエンスの普及に貢献していきたいです。キャリア面では、現在toB向けのソリューション提供の仕事に関わっているので、社内の優秀な方々と一緒に働いて、ビジネスとしての知見を深めスキルアップしたいなと思っています。
ーーこの夏、私たちUdemyでもデータコンペ「atmaCup #20 in collaboration with Udemy」を開催します。このような実践的な学びの場づくりに関して、期待することはありますか?
村上:
今後データサイエンスを学びたい方向けにどのような場があると良いかという視点でお話すると、初心者でも参加しやすいコンペがもっと増えるといいですね。Kaggleなどのコンペについては年々参加者の参入障壁が上がっていっているなという実感があります。プラットフォーム自体が特殊だったり、コンペのタスクも複雑なものが増えていたり。
atmaCupは、初心者向けの講座が開催されたり、短期間で参加しやすかったり、ディスカッションを通した参加者同士の知識共有も活発で、非常に魅力的です。このように、盛り上がりもあり質も高く勉強になるデータコンペが頻度高く開催されることを期待しています。新規参入の方が増えるとよりコミュニティも盛り上がっていくと思うので。
みなさんへのメッセージ
ーー最後にお二人から、組織の人材育成を担う担当者やコンペ参加を通じたスキルアップに興味のある社員の方に向けて、ひと言メッセージを頂けますか?
藤川:
自社の事業において良い技術やスキルを提供するというミッションは、どんな組織でも共通しているのではないでしょうか。そんな中で、メンバーが自走して先端技術やスキルを身に付けることは、組織の活性化や成長にもつながります。社員の成長や能力育成支援に関する制度構築の一例として、私たちの取り組みを役立てて頂ければ嬉しいです。
村上:
迷ったら、まずはコンペに出てみましょう。とにかくコンペに出ると勉強になります。とりあえず出てみて気になったことを学んでいくのがおすすめです。近々では初心者向けのコンペや学習コンテンツ、様々な参考記事やUdemyの講座なども増えていると思うので、そういったものも活用しながら参加して頂けると良いかと思います!
あなたもデータコンペに参加してみませんか?
atmaCup #20 in collaboration with Udemy開催!
atmaCupは、初心者から上級者まで幅広く参加できるデータ分析コンペです。
開催期間中、データサイエンティストによる初心者向けの勉強会をライブ配信するなど、初学者も含めて全員がデータ分析の面白さを体感できるようなコンペを実施しています。
私たちベネッセコーポレーションでは、Udemyの動画学習講座などで学んだことを実践的に活用する場を提供したいという思いから、この夏 atmaCup #20 in collaboration with Udemyを開催します。チーム(3人まで)でも個人でも参加可能。組織の人材育成の機会として、自身の学びをアウトプットする場として、まずは一度、atmaCupに参加してみませんか?
企業の人材育成担当者のみなさまも、ぜひ自社のデータサイエンティストの挑戦を応援してください!
atmaCup #20 in collaboration with Udemy
👉詳細・お申し込みはこちら
■開催概要:
開始日時:2025年7月25日(金)開会式(16:00~)
終了日時:2025年8月4日(月)閉会式・結果発表(16:45~)
※オンライン実施
★入賞者には、2025年8月29日(金)15:30より表彰式&振り返り会(懇親会付)を予定しております。(オンライン配信あり)
■参加対象者:
・仕事や趣味でデータ分析に関わっている方
・実データで分析をやってみたい方
・データコンペ参加に興味を持っている方
※個人もしくはチーム(3名まで)で参加が可能です。
※参加条件についてはお申込みページより詳細をご確認ください。
■問題設定:
課題は、データコンペ開始当日にオープンさせて頂きます。
■賞金:
・一般/初心者/ディスカッションの3枠合計11名(チーム)の表彰を予定
・一般枠1位の方には10万円の賞金をご用意
■初心者向け講座(YouTubeライブ配信):
・2025年7月26日(土)18:00-19:00
・2025年7月30日(水)16:00-17:00
※データ分析初心者向けの勉強会(オンライン/2回)を実施します。
👉詳細・お申し込みはこちら
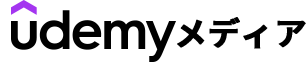
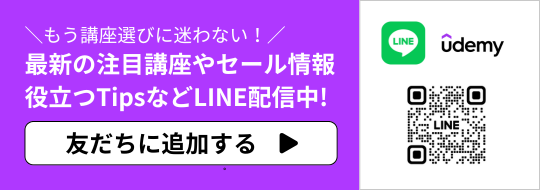


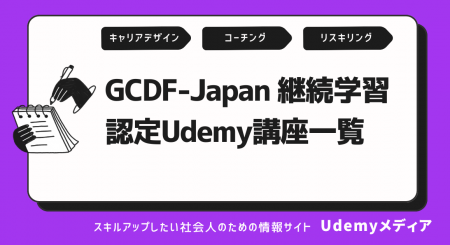

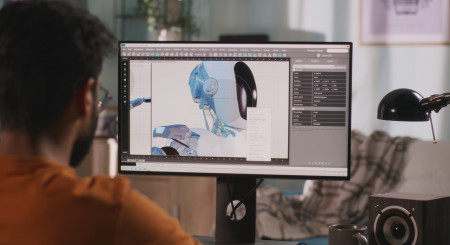



最新情報・キャンペーン情報発信中