atmaCup #20 in collaboration with Udemy 入賞者インタビュー
2025年7月25日(金)〜8月4日(日)にデータ分析コンペティション「atmaCup #20 in collaboration with Udemy」を開催いたしました。今回はデータ分析コンペへの参加経験に応じて初心者枠と経験者枠の2部門を設け、スコアを競いました。
本記事では、初心者部門で見事1位に輝いた北野さん(ID:kk0102)にインタビューを実施。応募のきっかけから期間中の取り組み、受賞後の思い、キャリアのお話しまで、幅広くお話を伺いました。

■北野 晃司さん
新卒でキヤノンITソリューションズ株式会社に研究開発職として入社。現在は、カメラやプリンター、複合機をはじめとするキヤノン製品の国内マーケティングに加え、ITソリューション事業を展開するキヤノンマーケティングジャパン株式会社に在籍。情報通信システム本部デジタル戦略部にて社内のDX推進を担当。
\文字より動画で学びたいあなたへ/
Udemyで講座を探す >INDEX
「ビジネス貢献のためのデータ分析」──データサイエンティスト職に就いてからのマインド変化
ーー現在、どういったお仕事をされていらっしゃいますか?
入社から現在に至るまで10年程データ分析業務に従事しています。キャリアのスタートはデジタルマーケティング領域におけるアクセス解析で、顧客分析やデジタル広告の効果分析を担当しました。その後、社内のECサイトのアクセス解析、より高度な分析業務、営業活動の行動分析、DX推進など、徐々に業務の幅を広げています。
ーーデータ分析のご経験が長いですが、バックグラウンドをお持ちだったのですか?
情報数理系の大学を卒業しており、大学では並列処理が研究テーマでした。研究開発をやりたいという気持ちで入社したのですが、データ分析業務に携わるようになってからは大きくマインドチェンジをし、研究的なデータ分析ではなく、ビジネス貢献するためのデータ分析ということを強く意識しています。データサイエンティストに求められる「ビジネス力」「データサイエンス力」「データエンジニアリング力」のうち、 私は「ビジネス力」が自身の一番の強みであると考えています。データ分析では、ほとんどの結果が「やっぱりそうだよね」とみんなが予想できる内容になることが多いですが、その中に1割くらいは新しい発見があります。そうした発見があったときに、嬉しさを感じるとともに、データ分析に取り組むことの楽しさを改めて実感します。
‟物事への興味”がキャリアの羅針盤──VUCA時代を生き抜く学びのスタンス
ーービジネスで扱うデータ分析を行うにあたってのスキルはどのように習得されたのですか?
大部分は業務の中で習得してきましたが、データ分析に関しては色々な書籍や著名な方々の情報発信なども数多くあるので、幅広く情報を拾っています。今はVUCA時代でもあるので、どのような状況にも対応できるように、自分の興味のある領域を広げていくことを目的に勉強している要素が強いです。「仕事は楽しくなきゃ意味がない、続かない」というのが私のモットーです。楽しさとは裏を返すと自分が興味を持てるかどうかだと思っています。色々なものに興味を持とうという意識だけは根本にあるので、結果として興味があるから学ぶ、学びが深まるという循環ができています。
ーー「仕事は楽しくなきゃ意味がない」北野さんならではの一つの価値観ですね。それはなにかきっかけがあったのですか?
特別なきっかけがあったわけではないのですが、社会人になってすぐにそのような考え方になっていたように思います。よく「趣味を仕事にするべきか」という議論がありますが、私は仕事を趣味にしてもいいのではないかと思っています。どうせ取り組むのであれば、自分が好きなように変えていけばいいし、自分がやりたい領域を広げていければ良いと考えています。仕事には多くの時間を費やすことになるため、それならば楽しい方が良いと思っています。もちろん、やるべきことはやるのですが、新しく取り組む領域においては自分がやりたいことに積極的に挑戦していくことを意識しています。
「自分ってデータサイエンティストとして胸張って名乗れるのか?」──初めてのデータ分析コンペ挑戦への思い
ーー今回コンペに参加された理由・きっかけは何ですか?
最大のきっかけは会社の制度として始まった「高度ITS人材認定制度」です。そこで私がデータサイエンティスト枠の第一号として認定をいただきました。一方で、これまでの業務においてはデータの可視化を中心とするBI(ビジネスインテリジェンス)領域の案件がかなりの数を占めていて、AIや高度な技術を使うような実績を積むことがあまりできていませんでした。そのような中で、外から見た時に「自分は本当にデータサイエンティストと胸を張って名乗れるのか?」という不安があり、実際に自信が持てないというのが本音でした。これまで積み重ねてきた実績を、自身の肩書きの信頼性につなげたいと考えていたところで、このコンペの情報を目にし、すぐに応募を決めました。
ーーコンペ自体の開催を知ったのはどのような経緯ですか?
以前、別のイベントに参加したことがあり、その際に届いたCompassの通知メールで知りました。たしか「短期間でのデータ分析コンペ」という文言が目に留まり応募したと思います。Kaggleのように3ヶ月~半年という比較的長期間取り組んで精度を上げなければいけないと、まだ気持ち的に参加ハードルが高いと感じていたのですが、短期間であれば集中して取り組めそうだと思い「気合い入れてやってみるか!」とチャレンジしてみることにしました。
短期集中で挑んだ11日間──成功のカギは仲間の発信
ーー11日間のコンペに取り組むうえで、戦略はありましたか?
短期間のコンペだからこそ、限られた時間を最大限に活用しようと考えていました。2週間弱という期間であれば、気合を入れて、土日や自分の時間を使って集中して取り組もうと決めました。平日は仕事の関係で2~3時間、土日は6時間ほど取り組みました。長期間のコンペだったら気持ちの面でも継続が難しかったと思います。
あとは、コンペに慣れている参加者の方々から学びながら、自分も積極的に取り組もうという思いで臨んでいました。せっかくディスカッション*という場があるのであれば、そこでさまざまな情報を目にして、自分で学びながら実装を試してみようという気持ちです。そのうえで、ビジネスの現場で培った自分なりの仮説構築力をプラスすることを意識しました。本当に偶然と言いますか、「やってみたら上手くいった」というところで自分でも入賞できたことに驚きました。
*ディスカッション:データ分析コンペの参加者同士、課題や分析方法について自由に議論、会話できる場。atmaCupの特徴であり、コンペプラットフォーム『ぐるぐる』上で投稿、やり取りができる 。
ーー期間中、苦労した点はありましたか?
Pythonで実装するところです。正直に言うと、かなり生成AIの力も借りたのですが、それでもエラーは出てしまい、そこはなんとか自力でエラー解消をしていたんですが、大変な時間はありましたね。楽しみながらやってはいたものの一瞬、ストレスを感じた点もありました(笑)なんで動かないの?ってGPTに文句言っちゃう場面もありましたね(笑)
実践でしか得られない学び──理論から一歩踏み込んだ、生きた技術の習得
ーーデータコンペにチャレンジされてみて、どんなことが得られましたか?
今回、機械学習的なモデルの実装というのが、技術的に求められるテーマだったかと思いますが、6~7年前にデータサイエンティスト協会が主催している養成講座を受講したことがあり、もともと機械学習の基礎知識や理論的な理解は持っていました。とはいえ、コンペでのディスカッションで効果検証の方法やアンサンブルの工夫など、精度を高めるための細かい実装テクニックを目にしてとても参考になりましたし、スキル・知見としても身に付きました。自分の経験だけでは得られなかったテクニックを、ディスカッションを通じて学び、実際に自分の実装に取り入れることができたのは良い経験だったと思います。
ーーコンペ後まだ日が浅いですが、この経験が業務につながったと感じることはありますか?
今回の入賞が新しいことに挑戦するモチベーションにつながったと思います。入賞したことをその日の夜に、社内のチームチャットに投稿しました。参加したことを伝えていなかったので周囲は驚いていました。
AI・データ分析を正しく広めたい・・・!コンペ挑戦から見えた次なる挑戦
ーーこれからデータ分析コンペやデータ分析にチャレンジしたいと思っている方に向けて、このデータ分析コンペに参加してこれはよかったなと思う点、アドバイスをお願いします
たくさんありますが、やはりディスカッションの場があったということが一番大きかったです。データコンペに参加して、さまざまな方の考えや意見に触れることができました。単に新しい技術を吸収できただけではなく、今回のテーマに対しても自分自身、仮説構築力にはある程度の自信をもって取り組んでいましたが「他の人だったらこういう見方をするんだ」と異なる視点に触れられたことが良い刺激になりました。
あとこれは社内でもよく伝えているのですが、「データ分析=難しいもの」と考えてほしくないと思っています。「データ分析をやろうとしたら統計学の知識が必須なんだよね」「AIを使いこなせないとダメなんだよね」って思わないでほしいなと思います。事業会社にいるデータサイエンティストとして強く感じるのが、データ分析はあくまで‟ビジネス価値を生み出すための道具”だということです。もちろん理論や技術も大事ですが、それ以上にまずはビジネス上の課題を見つけ出す力を磨いていくことが大切で、その上でデータ分析に挑戦するという意識が大事だと思います。だからこそ、最初の一歩として、まずは自分が直面しているビジネス課題や関心のある社会課題に対して「データ分析でこんなことができるかもしれない」と考えてみるところから始めてみるのが良いのではないかと思います。
ーー今後身につけたいスキルや挑戦したいことを教えてください
手段が目的化しないよう気を付けつつも、高度な分析が必要なテーマを自分で見つけて取り組んでいけたらなと思っています。私はデータ分析に加えて、社内DXに関する情報発信も担当しています。今後は、認定者として、「データ分析でこんなことができる」ということを詳しく紹介する場を設ける予定です。そこから「自分の組織だったらこんな分析ができそう」といった相談が自然に生まれてくれば、その中から高度な技術が活かせるテーマを見つけて提案につなげていけるのではと期待しています。社内では「AIは何でもできる」「魔法のようなツール」といった過度な期待も感じられますが、そうした認識があるからこそ、うまく活用できていないのが現状です。まずはAIで何ができるのかを正しく理解してもらい、ひとつ成功事例を作る。そしてそれを横展開していく、そんな進め方ができたらと考えています。今回のようなきっかけが、良い事例となり、横展開につながっていく流れを作れたらと期待しています。
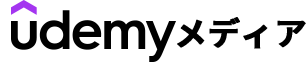
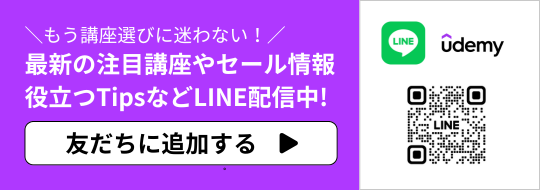





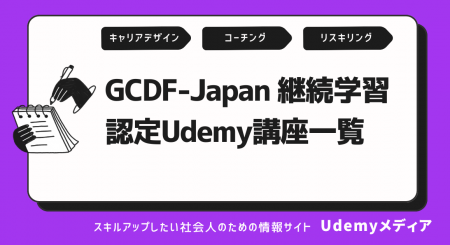

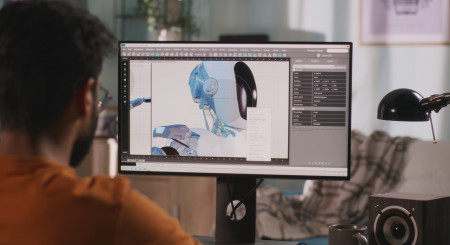



最新情報・キャンペーン情報発信中