atmaCup #20 in collaboration with Udemy 入賞者インタビュー
2025年7月25日(金)〜8月4日(日)にデータ分析コンペティション「atmaCup #20 in collaboration with Udemy」を開催いたしました。
今回は、オンライン動画学習プラットフォーム「Udemy」を運営する米国Udemy社とベネッセの業務提携10周年を記念した特別開催として、atma株式会社とともに実施。初心者枠と一般枠の2部門にて多くの皆様にご参加いただきました。
ご参加いただきました皆様、ありがとうございます。
本記事では、一般枠で見事1位になったTaichicchiさんこと藤井さんにインタビュー。コンペを通して学ぶ楽しさが、自己成長につながる秘訣を伺いました。

■藤井 太一さん
金融機関向けのシステム開発を手がける株式会社FBSに新卒入社。データ分析、AI、ブロックチェーンといった先端技術の活用を積極的に進める同社にて、一貫してデータサイエンティスト職に従事。
\文字より動画で学びたいあなたへ/
Udemyで講座を探す >INDEX
データ分析の仕事は7年目。コンペ参加は「学び」のため
── 現在、どのようなお仕事をされていますか?
大学院で統計学を研究していて、データサイエンスや統計分析に関わる仕事がしたいと思い、新卒でFBSに入社しました。今年で7年目になります。
弊社はもともと金融機関向けのシステム開発がメインでしたが、近年はヘルスケア領域にも事業を広げています。私はAIやデータサイエンスを扱う部署で、銀行のアンチマネーロンダリング業務を支援するAIモデルや、医療機関向けのシステム開発などに携わってきました。
データサイエンティストとしての側面もありつつ、機械学習を使ってデータ加工ソフトやシステムを構築するシステムエンジニアの側面もある。そんな仕事です。
–今回atmaCupに参加されたのはなぜでしょうか?
ここ最近はあまりコンペに参加できていなかったので、そろそろ新しい学びを得たいと思っていたんです。SNSでatmaCupの開催を知って、11日間という短期間で集中して取り組めるのがいいなと思いました。
これまでも定期的にコンペには参加していて、atmaCupは今回で4回目、Kaggleでもシルバーを2つ獲得しています。
–参加するコンペはどのように選んでいますか?
開催情報はデータ分析界隈の方々のSNSを見て知ることが多いです。その中から、私生活を犠牲にしてまで、というタイプではないので、余裕がある時期に参加すること。そして、どうせ参加するなら何か学びを得たいので、新しい知識が得られそうな題材を選ぶようにしています。
「これが効きそう」がスコアに繋がる!コンペは、「楽しさ」が生み出す成長のサイクル
–コンペ参加のモチベーションは何でしょうか?
一番は、やっていて「楽しい」ということです。スコアが上がるのももちろん楽しいですが、それ以上に「これが効きそうだな」というアイデアを出して、試して、実際にスコアが上がったときの一連の流れがすごく面白い。「綺麗に決まったな」と感じられたときの達成感はとても大きいですね。
コンペは、学びの場でもあります。データ分析や機械学習の技術はどんどん新しくなるので、普段の業務ではなかなか追いつけません。でも、コンペに参加して知らなかった新しいモデルを知ることができたり、論文や実装を調べる中で理解が深まったりする。実際に手を動かして挑戦できるのが大きな学びになっています。
私は効率的に体系立てて学ぶタイプではなく、コンペを通じてその都度必要な知識を吸収するスタイルです。それが自分には合っていて楽しく続けられるから、参加しているという感じです。
–コンペ参加が業務に活きた経験はありますか?
入社1、2年目の頃、金融機関向けの機械学習モデルを作る業務に携わっていたのですが、その時はKaggleで得た経験がほぼそのまま活きました。テーブルデータから目的を予測するような典型的なプロジェクトだったので、Kaggleでやった実装を業務に落とし込むだけで済んだんです。これは非常に良い経験でした。
あとは単純に、コンペでPythonを書いてきたから実務でもスムーズに書ける、というような、直接的ではないけれど、手を動かした経験そのものが回りまわって役立つことは多いですね。
短期集中で1位に。限られた時間で成果を出す効率的な攻略法
–参加にあたっての戦略や工夫があれば教えてください
コンペ期間の前半はあまり時間が取れそうになかったので、効率的に進めることを意識しました。まずはディスカッションで良い情報がないかチェック。そこで、自分がキャッチアップできていないモデルに関する参加者の方の記事が目にとまり、それを重点的に調べることにしたんです。
私は完璧主義に近くて、サブミッションを多くするというよりは、自分が納得できるパイプラインをしっかり作ってから提出するタイプです(今回は50回中30回)。納得できるベースができたら、そこからパラメーターを変えたり、試したいアイデアを加えていったり。アイデアが出るたびに修正を加えていく、というやり方でした。
–新しいモデルのキャッチアップはどう進めましたか?
基本的にはディスカッションで見つけたものをネットで調べ始めます。論文に当たれそうだったら読んでみて(難しくて挫折することも多いですが)、疑問があったら最近はChatGPTに壁打ちしてます。「仕組みは?」「最新は?」「もっと細かいディテールを解説して」とどんどん質問して、理解できるまで噛み砕いていく、という感じです。
–限られた時間でどんなスケジュールで取り組みましたか?
平日の夜、1~3時間くらいでやっていました。忙しい社会人にとって、限られた時間をどう工夫するかがポイントで、今回は学習に時間がかかる大きめのモデルを使ったので、仕事中に重いスクリプトを回しておいて、夜に結果を見てサブミットするかどうかを決める、といった進め方をしていましたね。
–参加してよかったポイントはありますか?
やはりディスカッションです。ソースコードを共有してくださる方も多く、とても気づきが多かったです。前半に時間が取れず、データの可視化や傾向分析が十分にできなかったので、ディスカッションで補いながら進められたのが本当に助かりました。
–新たに得られた気づきや知見はありましたか?
自然言語処理の新しいモデルをキャッチアップできたのは大きかったですね。あとは、今回のコンペは、ローカルスコアやパブリックリーダーボードにオーバーフィットしないサブミッションをどう作るかという試行錯誤を繰り返しました。その「感覚」を得られたのは大きな収穫です。
–今後、業務にも活きてきそうでしょうか?
そうですね。直接的なスキルだけでなく、仕事の取り組み方のベースがコンペで培われていると感じます。コンペでは、仮説を立て、実験し、結果を出すサイクルを高速で回すのですが、この「仮説思考」が日常の業務の進め方にも活きてくると思います。
忙しい中でも工夫して挑戦した経験自体が、成長につながる大きな財産になりました。
コンペで得た知見を社内へ還元。未来を見据えた挑戦
–今回のご経験は社内でも共有されるのでしょうか?
今は一部にしか伝えていませんが、いずれ全社に向けて報告したいと思っています。ノウハウをシェアすることはもちろん、今回1位をいただけたという事実自体も、採用活動や対外的な取り組みに活かせるのではないかと考えています。
–普段、社内ではどのように学んでいるのでしょう?
社員同士での情報交換や勉強会は活発に行われています。私自身もこれまで自然言語処理や勾配ブースティングなどについて勉強会を開き、知識を共有してきました。今回コンペで得た知識も、ぜひシェアしていきたいですね。
–今後社内でチャレンジしてみたいことはありますか?
これからホットになっていく分野に積極的に身を置いていきたいと思っています。具体的には、今だと生成AIをどんどん使っていくような仕事がしたいです。社内にそうした案件がないか、常にアンテナを張っています。
コンペで培った経験を活かして、スピーディーに開発したり、データ分析で良い示唆を得られたりする瞬間を増やしていきたいです。
「まずはデータコンペ参加ボタンを」──迷っている人に伝えたい、最初の一歩の踏み出し方
私が初めて参加したコンペはKaggleだったのですが、サイトは全部英語で、何を言っているのかもわからず、何とか調べながら食らいついて、とても大変でした。
でも、一度出てみたらそれが良いきっかけになって、次も似たようなコンペを探すようになりました。自分が興味のある分野や、これまでのバックグラウンドに近い題材から挑戦してみるのは、すごくいい方法だと思います。
最近は生成AIの普及で、コーディングやアイデア出しのハードルがどんどん低くなってきています。だからこそ、身構えすぎずに、まずは「参加」ボタンを押してみてください。一歩踏み出してみれば、きっと想像以上の学びや面白さに出会えるはずです。
データコンペで「学び」と「楽しさ」を両立!Udemyはあなたの自己成長を応援します!
藤井さん、そしてatmaCupにご参加いただいたみなさん、本当にありがとうございました。 入賞者の声はいかがでしたでしょうか?データコンペは、楽しみながら自然とスキルが身につく最高の「学びの場」であることが伝わったのではないでしょうか。 Udemyは、挑戦するすべての人の自己成長をいつでも応援しています。藤井さんがコンペで新しい知識を吸収したように、あなたの「学びたい」という気持ちを、Udemyはいつも全力でサポートします。 さあ、次はあなたの番です。Udemyと一緒に、自己成長の扉を開けてみませんか? Udemyとベネッセの業務提携10周年を記念し、実践的な学びの場を提供したいという思いで開催したデータ分析コンペ:atmaCup! 開催の背景やコンペの楽しみ方などをまとめています。以下の記事も、ぜひチェックしてみてください!
– atmaCup #20 in collaboration with Udemy|振り返り記事
atmaCup #20 in collaboration with Udemy データ分析コンペティション開催レポート —データサイエンティスト育成を加速する、“学びと実践”のコンペティション—|Udemy(ユーデミー)
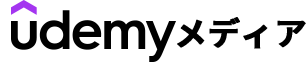
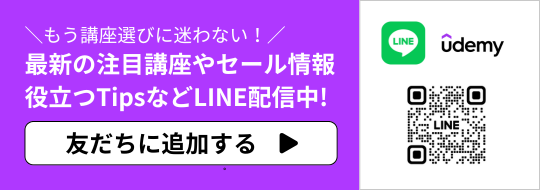





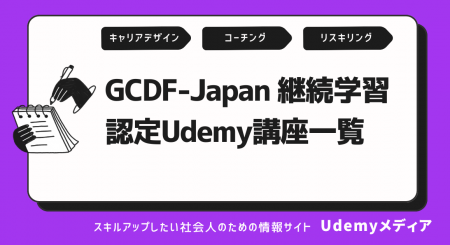

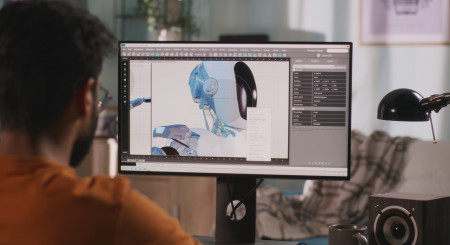



最新情報・キャンペーン情報発信中