SAPの活用を検討しているものの、
・SAPの特徴が分からない…。
・どのようなことができるか知りたい…。
という方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、
・SAPやERPの意味や機能
・SAPの導入事例
についてご紹介します。
初心者の方でも、この記事を読めば、SAPやERPの概要について理解できます。
\文字より動画で学びたいあなたへ/
Udemyで講座を探す >INDEX
SAP(エスエーピー)とは?
SAPとは、1972年にドイツで創業された大手ソフトウェア開発企業のSAP社と、SAP社のERP製品の両方を指す言葉です。
創業当時の英語名である「System Analysis Program Development」の頭文字をとってSAPと呼ばれるようになりました。企業と製品のどちらを指す場合も、読み方は「エスエーピー」であり、「サップ」ではありません。

ビジネスシーンにおいてのSAPは、主にERP製品を指すことが一般的です。SAP社のERP製品には、「SAP ECC (ERP Central Component)」や「SAP S/4HANA」など様々な種類があります。SAP社のERP製品については、後述の「SAPのERP製品の種類」で詳しく解説します。
業務に使用するシステムやデータを一元管理し、効率的に扱えるようになることがSAPを導入するメリットです。
\文字より動画で学びたいあなたへ/
Udemyで講座を探す >ERPとは?
ERPとは、従来の企業では別個に管理や情報共有が行われていた「会計」「人事」「生産」「物流」「販売」の5部門の情報を統合し、一元管理できるようにしたシステムです。
従来は、多くの企業で各部門が分断されていたことで作業量が増え、業務効率の低下や連携ミスなどの課題が発生していました。ERPの登場により、これらの問題を解決できるようになっています。
ERPは「Enterprise Resource Planning」の略称です。日本語で「基幹システム」や「統合基幹業務システム」と呼ばれることもあります。
SAPのERP製品の特徴、他社製品との違い
SAP社のERP製品には長い歴史があり、様々な国の企業で導入実績があることが特徴です。
SAPのモジュール(機能)は、各国の法制度や商習慣などに対応しているため、世界中のグローバル企業から信頼を集めています。近年では大手企業だけでなく、中小企業向けのソリューションも提供されるようになりました。
また、多くの企業がDX化に取り組む中で、多様なニーズを満たす製品が提供されていることもSAPの特徴です。SaaS型ERPやクラウド型ERPなど、より効率的にDXを推進できるシステムが提供されています。
SAP・ERPが普及した社会的背景
SAPのERPの導入が始まったきっかけは、1990年代前半に欧米で起こったBPR(Business Process Reengineering:業務プロセス改革)ブームです。この時期に、日本の企業でもERPパッケージが本格的に採用されはじめました。
その後、「2000年問題」や「Y2K問題」と呼ばれる、西暦2000年にコンピュータが誤作動するリスクが注目されたことで、情報システムを刷新するニーズがさらに高まっていきます。
このような社会的背景の中で、SAPのERPは企業ごとのニーズに対応できる基幹システムとして世界的に普及していきました。

SAP導入のメリットやできること
SAPを導入すると、経営に関する様々な情報を把握し、業務の効率化やコスト削減などに取り組めます。SAPのERP製品を使ってできることは次の通りです。
基幹業務
SAPでは、ビジネスにおける基幹業務を統合的に管理できます。財務会計や人事管理、購買管理、物流管理など幅広い分野の基幹業務を管理することが可能です。
経営状況や財務情報などのデータをリアルタイムに把握できるため、経営判断や意思決定を的確かつ迅速に行いやすくなります。
また、SAPは世界の優良企業が採用する業務プロセスをもとに開発されています。日本の企業では、業務を進める上で複数の承認が必要など非効率的な業務プロセスを取っている場合もありますが、SAPの導入によって業務を標準化できます。
ビジネスにおけるコスト削減
SAPを導入すると、ビジネスにおけるコスト削減効果も期待できます。
SAPで基幹業務を統合的に管理すると社内の情報を全社的に共有できるため、確認や連絡の手間が省けます。また、部門間の連携がスムーズになることで無駄な業務が減り、コストの削減が可能です。
社内情報の一元管理
部門内で完結している従来型の業務システムでは部門ごとにデータの形式が異なるため、部門間でのデータのシェアや活用が難しいことが一般的です。また、データの連携にタイムラグが発生する場合もあります。
一方、SAPではリアルタイムにデータを収集し、一元管理が可能です。業務に必要なデータを抽出してすぐに分析できるため、経営判断を迅速に行えるようになります。
SAP導入のデメリットや注意点
SAPを導入する際には、導入費用の高さや操作の難しさといった以下の点に注意が必要です。
ここでは、SAP導入のデメリットや注意点について詳しく解説します。
導入費用が高額である
情報システムを社内に置くSAPのオンプレミス版を導入する場合は、初期費用のほかに、ソフトウェアのライセンス料金やサーバ費用、システム構築料金がかかります。
クラウド版ではオンプレミス版と比べて初期費用は低くなるものの、サブスクリプション費用がかかるため、長期運用する場合には高額になります。
これらのコストがかかるため、SAPの導入費用として1,000万円~3,000万円ほどの予算が必要です。
機能や設定が豊富なため操作が難しい
SAPには、モジュールごとに機能や設定が豊富に用意されているため、操作が複雑に感じられる場合があります。
SAPは「ABAP」という独自のプログラミング言語で構築されています。そのため、ABAPを扱える人材を雇ったり、専門家からのレクチャーを受けたりするなどの対策が必要です。
事前にSAPへの理解を深めておく必要がある
前述の通り、SAPには複雑な機能が備わっていて、操作には専門的なスキルが求められます。SAPを導入しても、システムを適切に運用できなければ、業務効率化などを達成することはできません。
そのため、事前にSAPへの理解を深めておく必要があることが、注意すべきポイントです。マニュアルの整備や、SAPの運用経験がある人材の採用の事前準備が必要となります。

SAPのERP製品の種類
SAPのERP製品は、種類によって機能や対象企業などが異なります。SAPの主なERP製品の特徴は次の通りです。
- SAP ECC (ERP Central Component)
- SAP S/4HANA
- SAP S/4HANA Cloud
- SAP Business ByDesign
- SAP Business One
一つずつ簡単に説明します。
SAP ECC (ERP Central Component)
従来からあるオンプレミス型のERPシステムです。財務会計や在庫管理、生産管理といった機能がモジュールごとに利用できます。
ただし、2027年をもって保守が終了予定であるため、SAP S/HANAなどへの移行が推奨されています。
SAP S/4HANA
データの高速処理が可能となった次世代型のERPシステムです。各部門で管理する様々な情報をリアルタイムに分析し、業務効率化に取り組めます。
SAP S/4HANA Cloud
SAP S/4HANAと同様の機能をクラウド型で利用できる製品です。ベンダー側でシステムのアップデートが行われるため、保守の負担を抑えて運用できます。
SAP Business ByDesign
中堅企業向けに提供されるクラウド型のERPパッケージです。財務や顧客関係管理、プロジェクト管理などを効率的に行うための機能が備わっています。
SAP Business One
中小企業向けのERPソリューションです。オンプレミス型とクラウド型の両方があり、自社のニーズや事業規模に合わせて導入できます。
【著者が教える】これだけは知っておきたいSAP関係用語【100】~SAP入門者が覚えておくべき基本用語を解説~

「聞きなれない専門用語‥」「どこから覚えよう…」そんな方に向けて、本講座では、ERP/SAP/簿記/会計 +税務/社会保険の業務を身につける上でおさえておきたい用語100をピックアップして解説します。
\無料でプレビューをチェック!/
講座を見てみる
SAPのERP製品に備わっているモジュール(機能)
SAPのERP製品は、各分野の業務に必要な機能をまとめたモジュールによって構成されています。SAPに含まれる主なモジュールは次の通りです。
- 財務会計(FI:Financial Accounting)
- 管理会計(CO:Controlling)
- 固定資産管理(FI-AA:Asset Accounting)
- 人事管理(HR:Human Resources)
- 生産管理(PP:Production Planning and Control)
- 品質管理(QM:Quality Management)
- 販売管理(SD:Sales and Distribution)
- プラント保全(PM:Productive Maintenanceなど)
- 在庫購買管理(MM:Material Management)
各モジュールについて簡単に説明します。
財務会計(FI:Financial Accounting)
企業の財務状況を管理できるモジュールです。仕訳や帳簿の管理、決算処理、財務報告書の作成などの機能が備わっています。
管理会計(CO:Controlling)
コストや収益を管理するためのモジュールです。原価計算や予算管理、製品やプロジェクトごとの収益性の分析などができます。
固定資産管理(FI-AA:Asset Accounting)
企業の固定資産を管理するためのモジュールです。資産の取得や償却の管理、資産報告のための機能が含まれます。
人事管理(HR:Human Resources)
人材の管理に関するモジュールです。勤怠管理や給与計算、従業員情報の管理などができます。
生産管理(PP:Production Planning and Control)
生産計画や製造プロセスを管理できるモジュールです。製造スケジュールの管理や生産計画の作成、生産実績の追跡などが可能です。
品質管理(QM:Quality Management)
製品の品質を管理するためのモジュールです。品質検査の計画やデータの分析、不良品の管理などを効率化できます。
販売管理(SD:Sales and Distribution)
販売業務全般を管理できるモジュールです。受注や出荷、配送の管理、請求書発行などの機能が備わっています。
プラント保全(PM:Productive Maintenanceなど)
設備の保全やメンテナンス業務を効率化するためのモジュールです。保守計画の作成やコストの分析などができます。
在庫購買管理(MM:Material Management)
資材の購買や在庫管理などを行うモジュールです。在庫の最適化や購買プロセスの管理などの機能が含まれます。

SAPの2025年・2027年問題と対応策
SAPの「2025年問題」や「2027年問題」とは、従来型のERP製品「SAP ECC 6.0」の保守サポートが終了することに伴う課題です。
もともとは2025年末に保守サポートの終了が計画されていたため、この課題は「2025年問題」と呼ばれていました。その後、サポート期間が2027年まで延長されたことで「2027年問題」と呼ばれています。
「SAP ECC 6.0」を導入済みの企業は、サポート終了までに次のような対応が必要です。
2027年問題の対応策
SAPの2027年問題への対応策は、大きく分けて3つあります。
1つ目はSAPの最新の製品への移行です。例えば、「SAP S/4HANA」などに移行すると、これまでのSAP運用ノウハウを活かせます。ただし、システムの移行にあたって一定の金額や時間、手間などのコストが必要です。
2つ目は他社のERP製品へ移行です。SAP以外にも様々な企業がERP製品を提供しているため、自社のニーズに合わせて乗り換えるという方法も考えられます。ただし、これまでに蓄積したSAPの運用ノウハウを活かしにくくなります。
3つ目は一時的に保守期限を延長して継続使用することです。現在設定されている保守基準料金に2%を追加すると、サポート期限を2030年末まで延長できます。ただし、新規機能の追加利用はできないことや、2030年にまた対応が必要になることがデメリットです。
自社で「SAP ECC 6.0」を利用している場合、上記のいずれかの対応を進めましょう。
日本企業のSAP導入事例
SAPは幅広い業界で活用できるシステムで、日本企業でも数多く導入されています。ここでは、日本企業のSAP導入事例を紹介します。
味の素グループ
味の素グループでは、SAPのERP製品を用いて、経営情報を分析するための基盤を構築しています。
タイ味の素社は「SAP Analytics Cloud」と「SAP Datasphere」の導入により、月ごとの業績の分析やレポート作成の業務時間を20%削減しました。
三井住友フィナンシャルグループ
三井住友フィナンシャルグループでは、グループ間での連携を強化するために、「SAP SuccessFactors」と「SAP Cloud Platform」を用いた人事プラットフォームを構築しました。
このプラットフォームにより、グループ内の各企業の人事情報を統合的に管理し、人材交流や情報連携をしやすい環境が実現されています。
キリンホールディングス
キリンホールディングスでは、DX化を推進するために経理、生産、物流という3つの領域でSAPを導入しました。部門ごとに構築されていたシステムをクラウド環境に移行し、SAPで統合管理を行っています。
さらに、今後は顧客データの管理にもSAPを活用する予定です。
SAPやERPの全体像を理解しよう
SAPを導入すると、財務や人事、販売といった様々な基幹業務を統合管理し、部門間の連携や業務効率化が期待できます。
SAPやERPに関する用語について効率的に学びたい方には、以下の講座がおすすめです。この講座では、SAPやERPのほか、業務を進める上で知っておくべき簿記や会計、税務、社会保険に関する基礎的な用語が100個紹介されています。SAPやERPの用語についてわかりやすく学びたい方はぜひ参考にしてください。
【著者が教える】これだけは知っておきたいSAP関係用語【100】~SAP入門者が覚えておくべき基本用語を解説~
レビューの一部をご紹介
評価:★★★★
コメント:コンパクトに全体像がまとまっています。コンパクトに全体像がまとまっています。ここを起点にして必要な部分を深堀していく入口にいいかな、と思いました。
専門用語を押さえて、自社に合ったSAPを選びましょう。
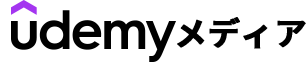


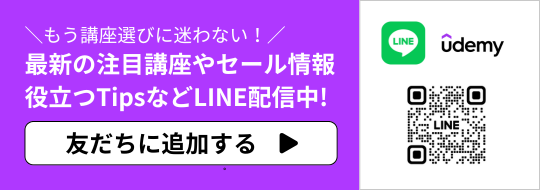



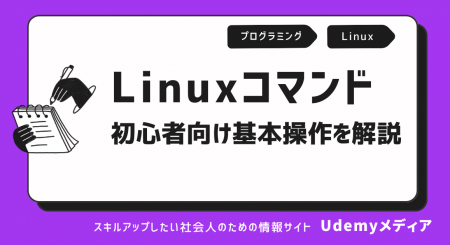
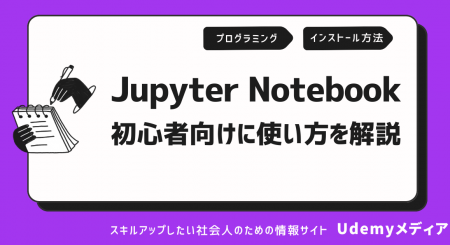
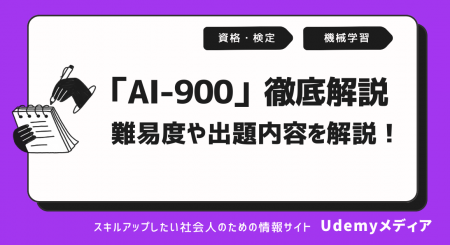
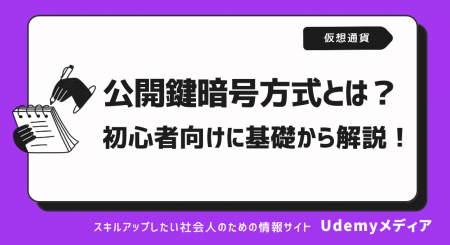
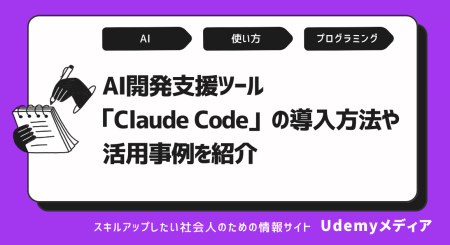



最新情報・キャンペーン情報発信中