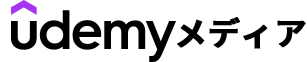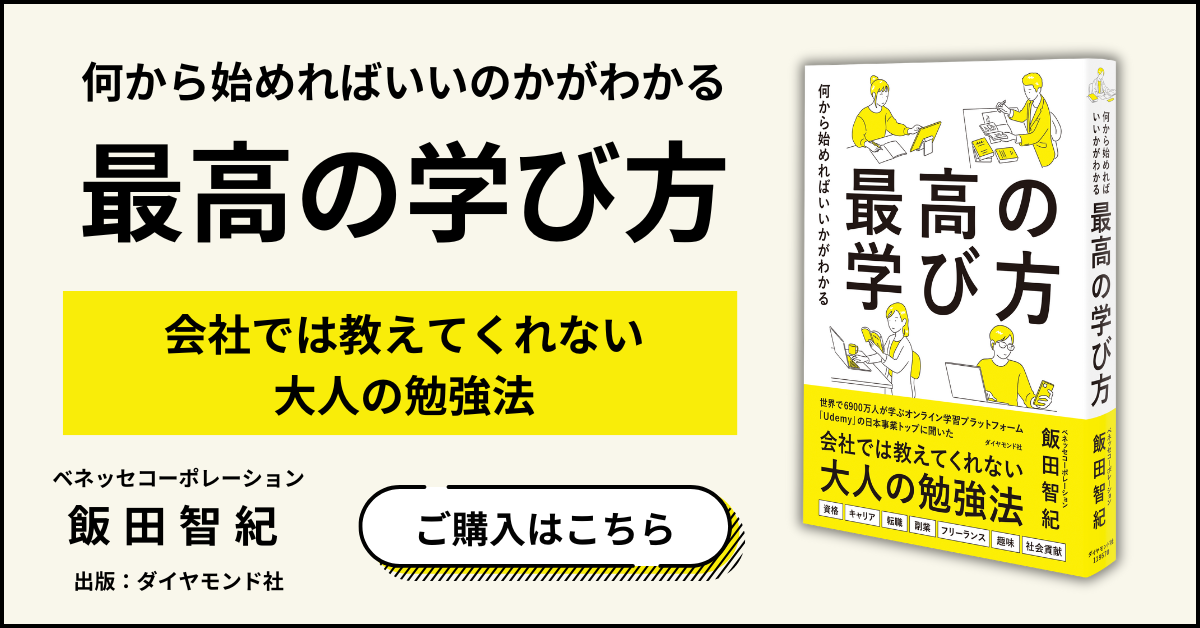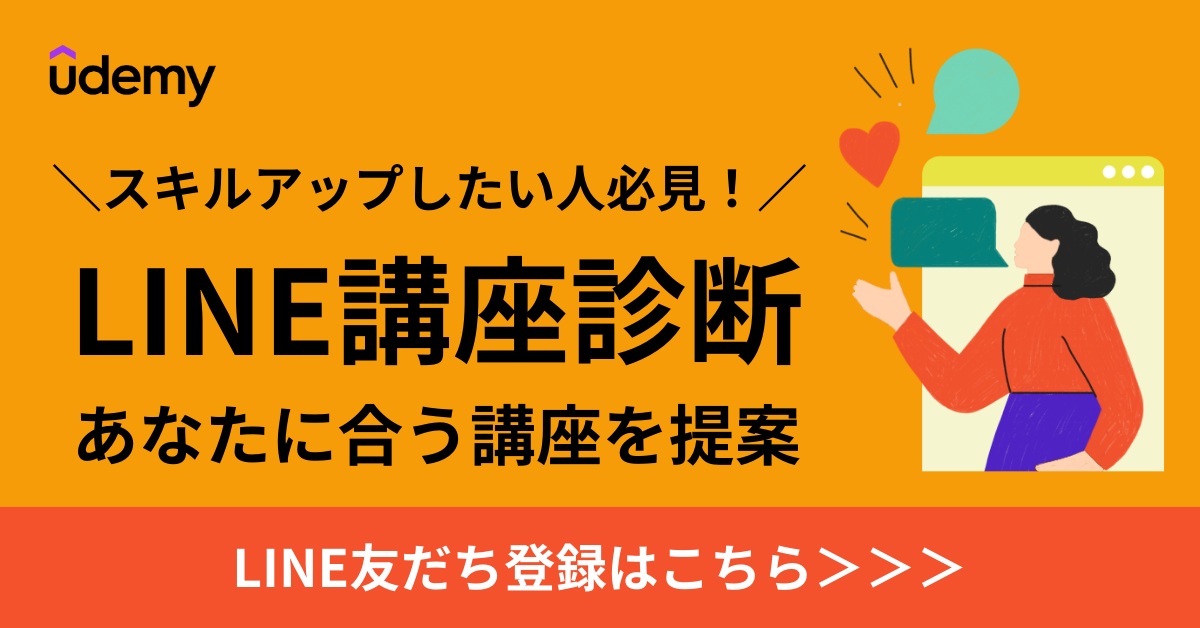- udemyメディア
- 学びを見つける
- 学びの成果体験談
- 30代インタビュー一覧
- 安井さんのインタビュー
高い視点からの学びを通して、
あらゆることの「最適解」を見出したい
- 30代
- エンジニア
- 正社員


-
Before
職業 マーケティング
役職 正社員
-
After
職業 エンジニア・PM
役職 正社員
取材にご協力いただいた方 安井梨沙子さん
学生時代からプログラミングや動画制作を学び、デジタルコンテンツ製作を仕事にしたいと希望していた、安井梨沙子さん。
ベネッセコーポレーションに入社後、マーケティング部門を経て、希望通り開発部門へ異動。現在はプロジェクトマネージャーとしてデジタル教材の開発に携わっています。
企画、開発など、立場の異なる人々とどのように的確なコミュニケーションを取っていくか。安井さんの学びの内容も大きく変化してきました。
モノづくりを仕事にしたいという強い思いで開発部門へ
イラストや動画制作、プログラミングに興味を持っていた安井梨沙子さんが進学先に選んだのは、プログラミングとデザインを学べる九州大学芸術工学部芸術情報設計学科でした。
大学ではiOSアプリやUnityでのゲームアプリの開発に没頭し、卒業後もデジタル教材の開発に携わりたいとベネッセコーポレーションに就職しましたが、最初に配属されたのはマーケティング部門だったそうです。
「中学生向け教材のダイレクトメールの企画・制作を担当することになりました。マーケティングについてはきちんと学んだことがなかったので、体系的に学ぶ必要があると考え、マーケティング・ビジネス実務検定の受験を決意しました」
企画提案をする際、裏付けとなる理論を学びたいと考えた安井さんは、専門書を購入。仕事に追われる中、通勤時間や業務終了後の時間を使って学習を続けました。約半年で資格を取得できたのは、目標としての資格取得があったこと、そして、仕事での企画検討会議など、学んだことをアウトプットする機会があったからだそうです。
入社4年目、安井さんは社内公募制度を活用して開発部門への異動を希望します。
「やはりモノづくりに関わりたいという思いが強かったのです。マーケティング部門でも、デジタル領域やSNS運営など、開発につながる仕事には積極的に手を挙げるようにしていました」
ここでも勉強の日々は続きます。
「とにかく(プログラミングの)知識がなければ何も進められません。仕事をしながら常に学び続けている状態でした」
幸いにも、先輩方が各言語や工程に関する専門書やUdemyの講座を教えてくれたので、迷うことなく学習を進められたそうです。
やがて安井さんは「こどもちゃれんじ」の動画教材のWeb開発に携わるようになり、設計/製造/テスト等の開発業務に従事するようになります。その際もUdemyを活用しましたが、会社で自由に利用できたため、興味のある講座を見つけては目を通し、その中から自分に合ったものを探し出して学べたことが良かったと振り返ります。

PMとして、部門内外のあらゆる立場の人々の理解を深める
現在、安井さんは中学生向けデジタル教材開発のプロジェクトマネージャーを務めており、新たな「学び」に挑戦しています。
まず、プロジェクトマネジメントについて体系的に学ぶべく国際資格であるPMP(Project Management Professional)の取得を目標に定めて現在学習中。目標設定と期限を決めて実践と並行で自らを追い込む学習方法は、マーケティング資格取得時の経験に基づいています。
安井さんが担当しているのは、1年以上の期間をかけて開発するウォーターフォール型のプロジェクトです。その名の通り、水の流れのように各工程の開発を計画的に順を追って進めていく手法ですが、同じ開発部門内には、アジャイル型でアプリを開発しているグループも存在します。短期間でアプリを形にし、実際のユーザーに使ってもらいながら、素早く改良・改善を重ねていく手法です。
「当初、ウォーターフォール型しか知らなかった頃は、アジャイル型の人々の動きに焦りを感じたり、進捗状況が気がかりだったりしました。しかし、書籍で学ぶことで、アジャイル型の理念やメリット、特有の進め方が理解できるようになり、打ち合わせで使われる言葉の真意も『なるほど、そういう意図だったのか』と腑に落ちるようになりました」
ウォーターフォール型とアジャイル型、手法は異なれど、学習する子どもたちにとっては同じ教材です。操作性をはじめとする統一感は不可欠です。お互いの理解を深める必要性を感じ、学びを深めました。
全方位的に考察した上で、「最適解」を見出したい
同じ開発部門内でさえ意思疎通に苦慮するのですから、異なる部門間でのコミュニケーションはさらに難易度が増します。安井さんがプロジェクトマネージャーを務めるプロジェクトには、開発部門のメンバーに加え、企画や営業などの事業部門のメンバーが多数関与します。
プロジェクト開始時に要件定義書を作成し、企画担当者の要望に沿って開発を進めますが、完成してみると「思っていたのと違う」ということは珍しくありません。
「共通言語がなく、伝わっていると思っていても十分にすり合わせができていなかったり、あとになって問題が発覚するリスクは大いにあります」
そこで安井さんは、完成品に近いイメージのプロトタイプを早期に用意し、企画と開発の間で同じビジョンを共有できるよう工夫しました。自らUdemyでプロトタイプ作成ソフトの使い方を学び、企画担当者や新人向けの研修も実施するようにしました。
企画側に必要なデータをあらかじめわかりやすく提示することも、立案に役立つはずです。
「子どもたちが教材をどのように使ったか、どんな反応を示したかなど、学習履歴やログデータを可視化すれば、企画にも活かせるはずです。開発としてそのようなデータを見やすくする工夫も行っています」
開発側にとっては、ユーザーリサーチが問題点の発見に役立ち、よい刺激にもなります。時には開発中の製品を一般の人に使ってもらい、感想を聞くこともあります。
「生活している環境が違う大人と子どもでは画面上での気になる観点も異なります。UI/UXを社内で検討した上で、必ず子どもや保護者の方に使ってもらい感想を聞くことがとても大切です。」
ユーザーは、開発側の意図通りに教材を使うわけではありません。開発側とユーザーの意識のギャップに驚きつつ、それを理解し、修正を加えていきます。
現在、安井さんが読む書籍は、仕事に直結する専門書はもちろん、歴史や哲学、社会の仕組みや成り立ちに触れたものまで、多岐にわたります。
その理由の一つは、立場の異なる人々を理解し、円滑なコミュニケーションを図りたいから。もう一つは、当たり前のように存在する世の中の仕組みを一度疑い、見つめ直したいと考えているからです。
「顧客の課題解決をする上で、営業、企画、そして開発メンバーは共創する必要があります。それぞれのプロフェッショナルが力を合わせていく過程で、自身が幅広い領域の知識を知り架け橋となることで、スピード感を持って議論を深めることができればと思っています」
あらゆる立場の人々を理解しつつ、あらゆる仕組みを見直しながら、「全方位的」に課題解決を図っていきたい。仕事でも家庭でも、もちろん社会全体でも、課題は山積みです。安井さんの「学び」は、これからも終わることなく続いていくのでしょう。
注目の講座
-

現役シリコンバレーエンジニアが教えるPython 3 入門 + 応用 +アメリカのシリコンバレー流コードスタイル
酒井 潤 (Jun Sakai)
4.4




 (22,487)
(22,487)
ベストセラー
-

Git: もう怖くないGit!チーム開発で必要なGitを完全マスター
山浦 清透
4.4




 (10,982)
(10,982)
ベストセラー
-

【2023年5月改訂版】実践 Python データサイエンス
Shingo Tsuji,Pierian Data International by Jose Portilla
4.1




 (7,712)
(7,712)
-

【2023年最新】【JavaScript&CSS】ガチで学びたい人のためのWEB開発実践入門(フロントエンド編)
【CodeMafia】 WEBプログラミング学習
4.6




 (7,252)
(7,252)
ベストセラー
-

ちゃんと学ぶ、PHP+MySQL(MariaDB)入門講座
たにぐち まこと(ともすた)
4.6




 (31,404)
(31,404)
ベストセラー
-

みんなのAI講座 ゼロからPythonで学ぶ人工知能と機械学習 【2024年最新版】
我妻 幸長 Yukinaga Azuma
4.3




 (13,297)
(13,297)
ベストセラー
-

【ChatGPT】使い方入門-生成AIをビジネス活用!初心者向け講座【Copilot,画像生成】2024年最新版
Youseful (ユースフル)
4.3




 (7,960)
(7,960)
ベストセラー
-

AIパーフェクトマスター講座 -Google Colaboratoryで隅々まで学ぶ実用的な人工知能/機械学習-
我妻 幸長 Yukinaga Azuma,Yuki Kashiwada
4.2




 (1,397)
(1,397)
-

ChatGPTのAPIで5つのアプリを作ってみよう!JSON生成、属性抽出、独自文書Q&A、SQL生成、AIエージェント
しま (大嶋勇樹)
4.5




 (236)
(236)
ベストセラー
-

【1日で学べる】専門用語を使わない「AI/人工知能」ビジネス活用講座
宏晃 森
4.2




 (4,593)
(4,593)
ベストセラー
-

【超初心者向け!】数学講師が教えるゼロからの統計学入門/データサイエンス・AIの基礎を身につけよう
シグマ先生 (数学テラス)
4.6




 (395)
(395)
-

【2023年5月改訂版】実践 Python データサイエンス
Shingo Tsuji,Pierian Data International by Jose Portilla
4.1




 (7,712)
(7,712)
最高評価
-

【世界で55万人が受講】データサイエンティストを目指すあなたへ~データサイエンス25時間ブートキャンプ~
365 Careers,株式会社CODOR (大橋亮太)
4.3




 (7,057)
(7,057)
ベストセラー
-

【ゼロから始めるデータ分析】 ビジネスケースで学ぶPythonデータサイエンス入門
株式会社SIGNATE (旧株式会社オプトワークス),Tomoki Takada(高田朋貴)
4.2




 (5,528)
(5,528)
-

【Python×株価分析】株価データを取得・加工・可視化して時系列分析!最終的にAIモデルで予測をしていこう!
ウマたん (上野佑馬)
4.3




 (1,904)
(1,904)
-

手を動かして学ぶプロダクトデザイン入門!デザイン思考・プロトタイピング・アジャイルの考え方と実践
箕輪 旭
4.1




 (6,851)
(6,851)
-

【Firefly対応】Illustratorを基礎からプロレベルまで 完全ですべてをゼロから学べる総合コース
むらもり こう(村守康)
4.3




 (4,349)
(4,349)
-

After Effects Class 初めてでも安心!現役クリエイターが教える動画コンテンツ制作術
OMOKAGE TV
4.3




 (3,799)
(3,799)
-

Photoshop 魔法のスーパテクニック No.11 超リアルなジグソーパズル
むらもり こう(村守康)
4.3




 (19)
(19)
ベストセラー
-

UXデザイン講座 UXデザイン基礎入門
萩本 晋
4.2




 (4,768)
(4,768)
-

元Appleエバンジェリスト、ガイ・カワサキの起業家塾(日本語字幕)
Guy Kawasaki
4.3




 (1,670)
(1,670)
ベストセラー
-

「営業の一流、二流、三流」の著者がお届けする、「誰もがトップセールスになれる!営業スキル大全」
伊庭 正康
4.6




 (3,074)
(3,074)
ベストセラー
-

【超入門】プロマネが教えるタスク・スケジュール作成の基礎
西村 信行
4.2




 (4,274)
(4,274)
-

【売れ筋講座TOP5選出!】いちばんわかりやすい決算書の読み方講座
公認会計士 川口宏之
4.5




 (3,855)
(3,855)
ベストセラー
-

【初心者から上級者まで】1日で学べるエクセルの教科書 マスターコース
熊野 整
4.4




 (24,187)
(24,187)
ベストセラー
-

はじめてのマーケティング ~豊富な事例をベースに理論の全体像を理解しよう!3時間半であなたもマーケター脳になれる
MindSeeds 丹羽 亮介
4.3




 (9,456)
(9,456)
ベストセラー
-

【数字を味方につける:初級編】ビジネスの現場で使えるデータ分析
齋藤 健太
4.2




 (9,227)
(9,227)
ベストセラー
-

【入門編】デジタルマーケティング初心者のためのKPI攻略講座~基本用語の理解から実践まで~
村上 佳代
4.3




 (3,505)
(3,505)
ベストセラー
-

GA4に関する知識を証明する!「Google アナリティクス認定資格」試験対策講座
木田 和廣
4.4




 (358)
(358)
ベストセラー
-

【60分速習】ChatGPTをフル活用して仕事の生産性10倍アップ!AIを味方につけてデキる人材になる!
谷口 恵子(タニケイ)
4.1




 (3,236)
(3,236)
ベストセラー
-

業界最先端の動画制作テクニックを制覇!Adobe Premiere Pro 完全版
OMOKAGE TV
4.5




 (4,785)
(4,785)
ベストセラー
-

【動画制作パーフェクトガイド】60講義26時間半!豪華特典あり!動画編集,撮影,照明,案件獲得まで動画の全てが学べる!
岩村 和輝
4.6




 (752)
(752)
ベストセラー
-

After Effects【脱初心者】タイトル・アニメーション8種+課題1種【モーショングラフィックス】
かも(kamo) /Eizou World Motion
4.8




 (459)
(459)
最高評価
-

DaVinci Resolve はじめてのカラーコレクション&カラーグレーディング オンライン講座
動画人 ターナー
4.5




 (237)
(237)
ベストセラー
-

【Unreal Engine5】サイバーパンクシティー制作講座
Yujiro Nomura
4.8




 (310)
(310)
ベストセラー
-

Webデザイナーのキャリアを未経験からスタートするためのオールインワン講座
Shunsuke Sawada
3.8




 (1,826)
(1,826)
ベストセラー
-

①ノーコードで超速WEB制作 STUDIO学習完全パック(初級編・中級編・上級編)
おたろう STUDIOでノーコードWEB制作
4.7




 (1,624)
(1,624)
ベストセラー
-

WEBデザイナーになりたい人のための【WEBデザイン入門講座】初心者を対象に基礎知識を入門レベルで幅広く学べる講座です!
K.Nakamura (storeG),storeG -web.com
4.3




 (6,968)
(6,968)
ベストセラー
-

【最新版】FigmaでレスポンシブWEBデザイン作り方!Figmaの基礎からWEBデザイン実践まで完全サポート
STAND 4U
4.6




 (402)
(402)
ベストセラー
-

HTML5&CSS3+JavaScript 講座【初級レベル】コーディングに自信のない方や独学者の復習に最適です。
K.Nakamura (storeG),storeG -web.com
3.9




 (532)
(532)
-

~始めから効率よく学ぶ~ 基本情報技術者試験 最速 合格講座
RYO IT
4.3




 (6,870)
(6,870)
-

【SAA-C03版】これだけでOK! AWS 認定ソリューションアーキテクト - アソシエイト試験突破講座
Shingo Shibata / AWS certified solutions architect, AWS certified …/p>
4.2




 (24,134)
(24,134)
-

ITパスポート最速合格コース ~効率的な学習で0から合格まで~
RYO IT
4.3




 (66,839)
(66,839)
-

【CLF-C02版】これだけでOK! AWS認定クラウドプラクティショナー試験突破講座(豊富な試験問題300問付き)
Shingo Shibata / AWS certified solutions architect, AWS certified cloud practitioner, AZ-900
4.2




 (12,835)
(12,835)
-

「PMP®認定試験」で一発合格を目指す! 効率的な試験対策のための戦略コース (2021) アジャイル対応
CLUTCH Management
4.3




 (4,273)
(4,273)
最高評価
-

【最初に学びたい】最新Blender3.3LTS 3DCGモデリング集中講座Part1
うめちゃん Umechan
4.6




 (3,610)
(3,610)
ベストセラー
-

【超入門編】Blenderで作る3Dアニメーションマスター講座! PCさえあれば無料でできる!
c-leon レオン
4.4




 (139)
(139)
-

Unity3D入門の決定版!RPG開発の基本をUnityインストラクターと共に進めるハンズオンコース【スタジオしまづ】
嶋津 恒彦
4.5




 (6,232)
(6,232)
-

【Unreal Engine 5の総合学習】ファンタジー風景制作講座
Yujiro Nomura
4.7




 (629)
(629)
-

初心者からの3Dキャラクターアニメーション完全マスター講座|キャラクターに生命を吹き込む!
Moco アニメーション
4.0




 (69)
(69)
-

【ChatGPT】初心者向け講座 ビジネスで活用できる程に返答の精度や品質を上げるコツを徹底解説【非エンジニア向け】
世界のアオキ (Akihiro Aoki)
4.2




 (5,624)
(5,624)
-

【累計40万部著者が教える】たった1日で!まったくの初心者でも最短でExcel VBAを仕事で活用できるようになる講座
吉田 拳
4.2




 (769)
(769)
-

「段取りのキホン」の著者が語るタイムマネジメント!オフィス&在宅での時間管理(リピート9割超の人気研修をWeb化)
伊庭 正康
4.2




 (10,875)
(10,875)
ベストセラー
-

独学で身につけるPython〜基礎編〜【業務効率化・自動化で残業を無くそう!】
安井 亮平
4.5




 (6,618)
(6,618)
ベストセラー
-

【はじめての Power BI 】データ分析プロジェクトの基本マスターコース
熊野 整
4.4




 (1,359)
(1,359)
最高評価
おすすめ記事
-

python for文を初心者向けに解説!for文基礎はこれで完璧
プログラミング言語pythonのfor文について、python初心者向けに解説します。
-

【初心者向け】 基本のLinuxコマンド一覧!操作別に紹介
ここでは、覚えるべき基本のLinuxコマンドを表にまとめて紹介します。
-

【初心者向け】Jupyter Notebookの使い方!インストール方法から解説
この記事では、Jupyter Notebookのインストールや基本的な使い方について、初心者にもわかりやすく解説します。
-

公開鍵暗号方式とは?初心者でもわかる公開鍵暗号方式の基礎
情報を守る代表的な方法である「公開鍵暗号方式」を紹介します。
-
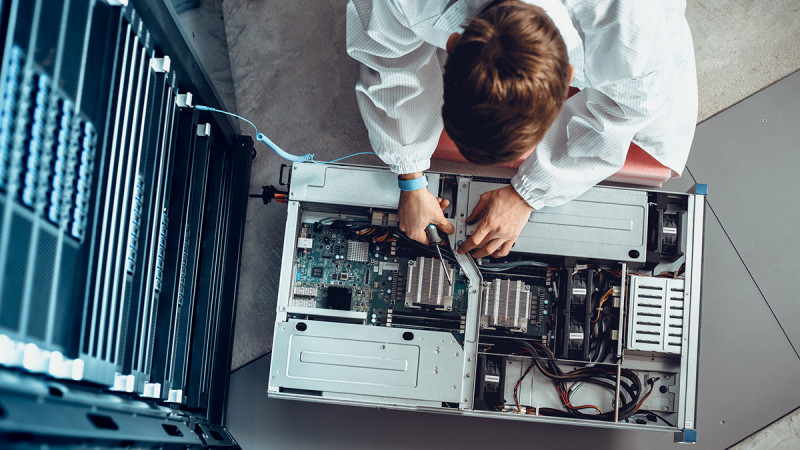
CCNAとは?どんな資格でどれくらい勉強が必要?時間の目安やおすすめサイトもご紹介!
2020年に改定されたCCNAの難易度や勉強時間の目安、おすすめの勉強方法などの資格取得に役立つ情報を紹介します。
-

ChatGPTを日本語表示で使用する方法!機能・使い方を解説
この記事では、ChatGPTの登録方法や日本語表示で使用する方法などについて解説します。
-

ニューラルネットワークとは?人工知能の基本を初心者向けに解説!
本記事では、近年の人工知能(AI)ブームを理解するための基本である「ニューラルネットワーク」について解説します。
-

Midjourney(ミッドジャーニー)の使い方!AI画像生成を体験しよう
Midjourneyの概要や使い方などについて詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
-
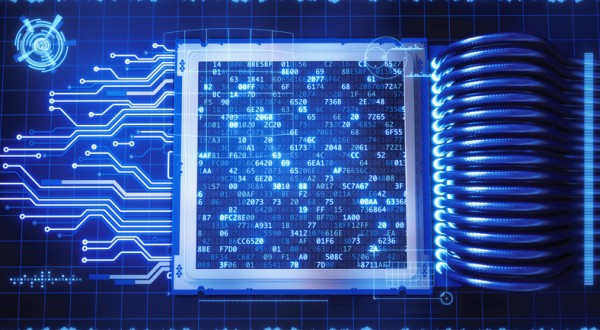
Pythonの拡張モジュール「NumPy」とは?インストール方法や基本的な使い方を紹介!
この記事ではNumPyの概要、またインストール方法から基本的な使い方まで詳しく解説します。
-

画像生成AI「Bing Image Creator」とは?特徴や使い方を徹底解説
Bingの画像生成AI「Bing Image Creator」の特徴や使い方、利用する際の注意点等解説します。
-

統計の中でも最重要分野のひとつ、t検定について徹底解説!
こちらでは、t検定の概要や手順、応用されている現場についてご紹介します。
-

重回帰分析とは?エクセルでもできる重回帰分析をわかりやすく解説!
今回は、回帰分析の手法の中から「重回帰分析」をご紹介します。
-

ChatGPTを日本語表示で使用する方法!機能・使い方を解説
この記事では、ChatGPTの登録方法や日本語表示で使用する方法などについて解説します。
-

Pythonでグラフ描画する方法を解説。Matplotlibを使えば簡単!
この記事では、Matplotlibの概要とグラフタイトルや軸ラベルの追加といった基本操作をご紹介します。
-

多変量解析とは?入門者にも理解しやすい手順や具体的な手法をわかりやすく解説
本記事では、多変量解析について、基礎的な知識から具体的な手法までわかりやすく解説します。
-

基本操作から応用まで!動画編集アプリCapCutの使い方を詳しく解説
この記事では、CapCutの使い方について、基本操作から応用まで詳しく解説します。
-

HTMLとは?初心者向けにタグの種類と使い方の基本を解説!
難しい専門用語を使わずに、わかりやすい画像や具体例を使って解説していきます。
-

イラレで画像を切り抜く(トリミング)方法2つと保存方法
今回はイラレでできる簡単な切り抜き(トリミング)の方法について紹介します。
-

Photoshopで背景を透明にする3つの技をスイスイ理解できる!
誰でも理解できるようにPhotoshopで背景を透明にして保存するための簡単な3つの技について紹介します。
-

3DCGソフト「Blender」の使い方!インストール方法から初心者向けに解説
この記事では、Blenderの概要やインストール方法、画像構成や基本的な使い方を詳しくお伝えします。
-

エクセルのCOUNTIF関数はどう使う?複数条件の扱い方も解説!
COUNTIF関数の使い方、複数の条件を扱う「COUTIFS関数」、「AND関数」「OR関数」を用いたCOUNTIF関数の応用についてお話します。
-

Word(ワード)をExcel(エクセル)に変換する方法!貼り付け後の形式崩れの防ぎ方
特別なソフトを使わずに、WordとExcelを変換する方法をご紹介します。
-

Excelで四捨五入ができるROUND関数の使い方と応用例を紹介
ROUND関数の初歩的な知識や使い方、端数処理に使うほかの関数に関してまでを解説します。
-

ExcelのIF関数の使い方!複雑な条件の指定方法をマスター
会社でよくある具体例やわかりやすい画像でお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
-

エクセルでグラフを作成する方法。棒・折れ線・複合グラフの簡単な作り方も!
グラフの特徴や基本的な作成・編集方法のほか、複数のグラフを複合させる応用手順をご紹介します。
-

仮説検定とは?計算の手順や用語をわかりやすく解説!
仮説検定の目的や用語の意味、計算方法について具体例を交えながら解説します。
-

エクセルを用いた統計処理のやり方って?分析ツール・関数を使った方法を紹介!
代表的な統計処理を、エクセルの分析ツール、または関数を用いる方法に分けてご紹介します。
-

KPIの意味とは?KPIの具体的な指標&目標達成のヒントも併せて解説
KPIのメリットや具体的な活用方法についてご紹介します。
-

ABC分析とは?エクセルのやり方を覚えれば在庫管理が楽になる
在庫管理が大幅に楽になる「ABC分析」をエクセルで実施する方法についてわかりやすくお話します。
-

マーケティング戦略とは?戦略の流れを5STEPで解説!使えるフレームワークもご紹介
マーケティング戦略の概要や実施するまでの流れ、また代表的なマーケティングフレームワークについて解説します。
-

基本操作から応用まで!動画編集アプリCapCutの使い方を詳しく解説
CapCutの使い方について、基本操作から応用まで詳しく解説します。
-

DaVinci Resolveの使い方とは?インストールから編集まで初心者にも分かりやすく解説!
DaVinci Resolveの概要やインストール手順、具体的な使い方について解説します。
-

DaVinci ResolveのFusionとは?基本的な使い方を解説!
実際に簡単なテキストアニメーションを作っていきながら画像付きで解説します。
-

After Effectsでアニメーションを付けてみよう!初心者でもわかる方法をご紹介!
今回は、After Effectsでできることやアニメーションの作成手順について解説します。
-

カラーグレーディング(カラグレ)のやり方を解説!カラコレとの違いや編集ソフト別のツールもご紹介
カラーグレーディングとは何か、カラーコレクションとの違い、おすすめのソフトなどについてまとめます。
-

HTMLとは?初心者向けにタグの種類と使い方の基本を解説!
難しい専門用語を使わずに、わかりやすい画像や具体例を使って解説していきます。
-

CSSとは?初心者にもわかりやすくCSSの書き方を解説!
「CSSとは?」「CSSって何なの?」という疑問を解消して頂ける内容となっています。
-
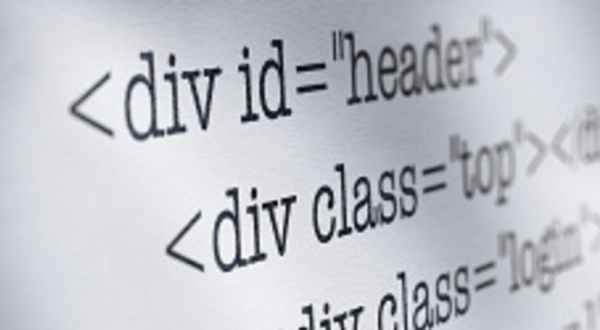
HTMLのdiv classとは?5分でわかる事例付き解説
「HTMLのdiv classとは」、「div classの使い方」などを具体例を用いて5分程度でわかる解説をご用意しました。
-

Canva(キャンバ)の使い方を初心者にもわかりやすくご紹介!
Canvaの機能や使い方を分かりやすくご紹介します。
-

CSS floatプロパティの基礎をわかりやすく解説!CSS初心者必見
CSSのfloatプロパティについて、HTML/CSS初心者向けに解説します。
-
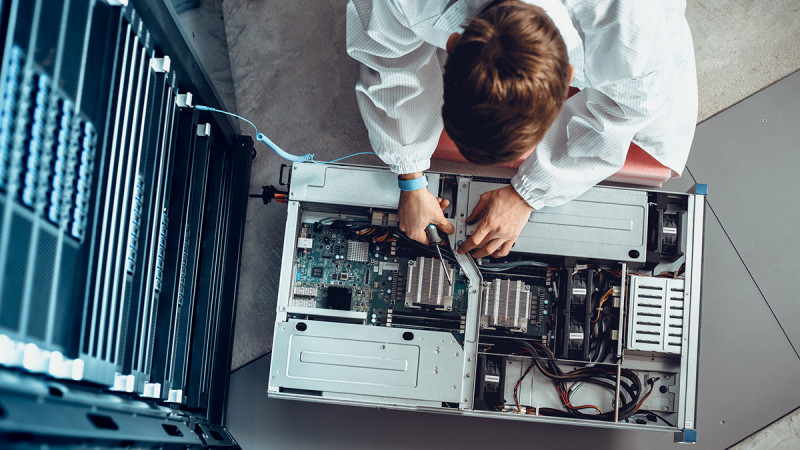
CCNAとは?どんな資格でどれくらい勉強が必要?時間の目安やおすすめサイトもご紹介!
CCNAの難易度や勉強時間の目安、おすすめの勉強方法などの資格取得に役立つ情報を紹介します。
-

PMP資格とは?難易度や取得方法、仕事上の価値についてわかりやすく解説
PMP資格取得のための効率的な勉強法と合わせて紹介します。
-

全11種類のAWS認定資格を難易度・分野別に一覧で紹介!取得メリットや勉強方法も
各試験の内容や受験料などの解説と併せて、初心者向けの学習方法も解説します。
-

Microsoft Azure認定資格を難易度別に解説!おすすめの勉強方法は?
Azure認定資格の概要から取得するメリットに加え、初級・中級・上級レベルに分けてAzure認定資格を紹介します。
-
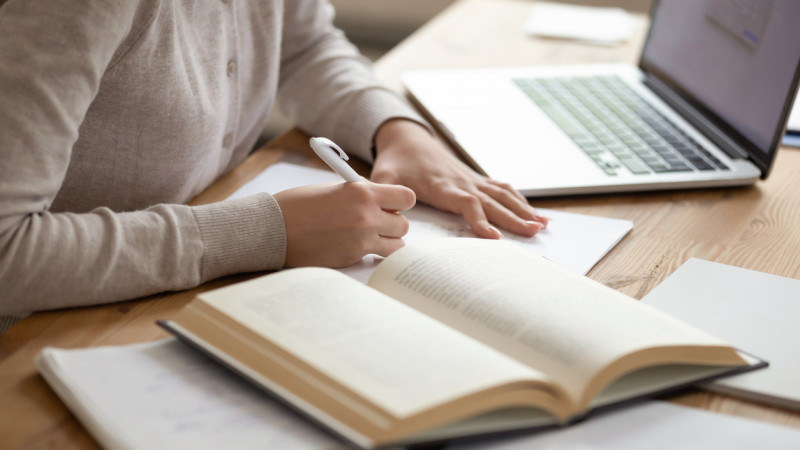
PL-900の難易度や受験のメリット・試験対策方法を解説!
PL-900の難易度や受験するメリット、おすすめの勉強方法などについて解説します。
-

3DCGソフト「Blender」の使い方!インストール方法から初心者向けに解説
Blenderの概要やインストール方法、画像構成や基本的な使い方を詳しくお伝えします。
-

【Blender】モデリングの基本操作を初心者にもわかりやすく解説
初心者の方向けにモデリングの手順を分かりやすく解説します。
-

Blenderのショートカットキーを覚えよう!一覧表もあり
この記事では、Blenderの視点操作やモデリングを効率化できるショートカットキーを紹介します。
-

【Unity】アニメーション作成の基礎を解説!回転の付け方・再生方法も
Unityの概要から簡単なアニメーションの作り方・再生方法まで、画像付きで解説します。
-

Unity入門!チュートリアルで学ぶ2Dアクションゲームの作り方
Unityで作る2Dゲームの特徴やメリット、アクションゲームの作り方を解説します。
-

【Outlook】メールアカウントの新規設定や署名の設定方法を解説!
メールアカウントを設定する手順や便利な機能、よくあるトラブルの対処法などを解説します。
-

【Googleスプレッドシート】初心者向けの使い方・共有・スマホ閲覧を解説
スプレッドシートの使い方や、エクセルとの違いなどをご紹介します。
-

Power Automate Desktopの使い方とは?スクレイピングやExcel自動化を実践!
Power Automate Desktopとは何か、またPower Automate Desktopの使い方について詳しく解説します。
-

Googleスプレッドシートとは?Excelと比較したメリットを解説
Googleスプレッドシートの使い方について、初心者の方にも分かりやすく解説します。
-

「Notion」とは?「オールインワン」万能アプリと呼ばれるその理由に迫る!
Notionの特徴や注目される理由、具体的な使い方について解説します。
Historyスキルと仕事ヒストリー
-
10代後半
プログラミングとデザインを学べる九州大学芸術工学部芸術情報設計学科へ進学。
-
20代前半
ベネッセコーポレーションに入社。通信教材のマーケティングを担当。
-
20代半ば
社内公募制度を利用して開発部門へ異動。「こどもちゃれんじ」の動画教材などの開発に従事。
-
20代後半
プロジェクトマネージャーとして「進研ゼミ中学準備講座」「進研ゼミ中学講座」のデジタル講座をはじめ開発管理へ。